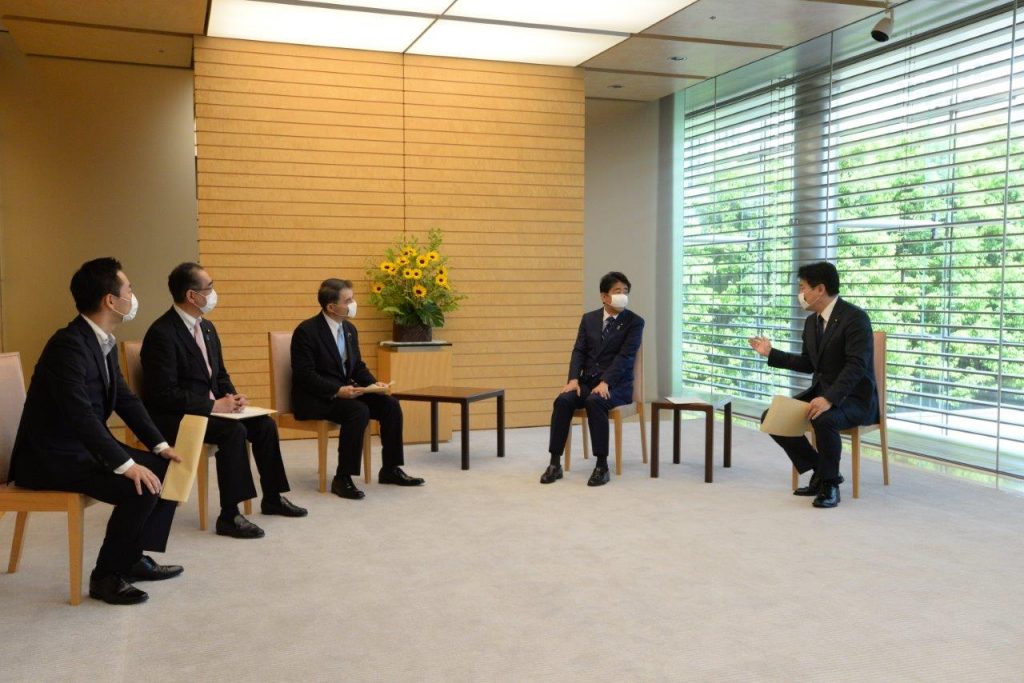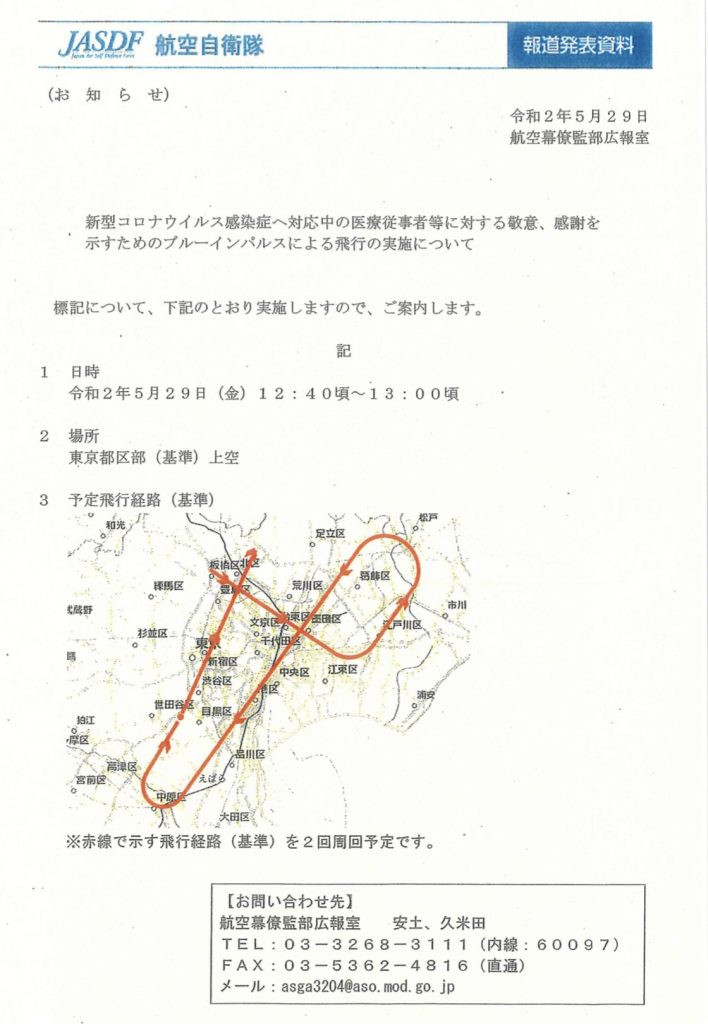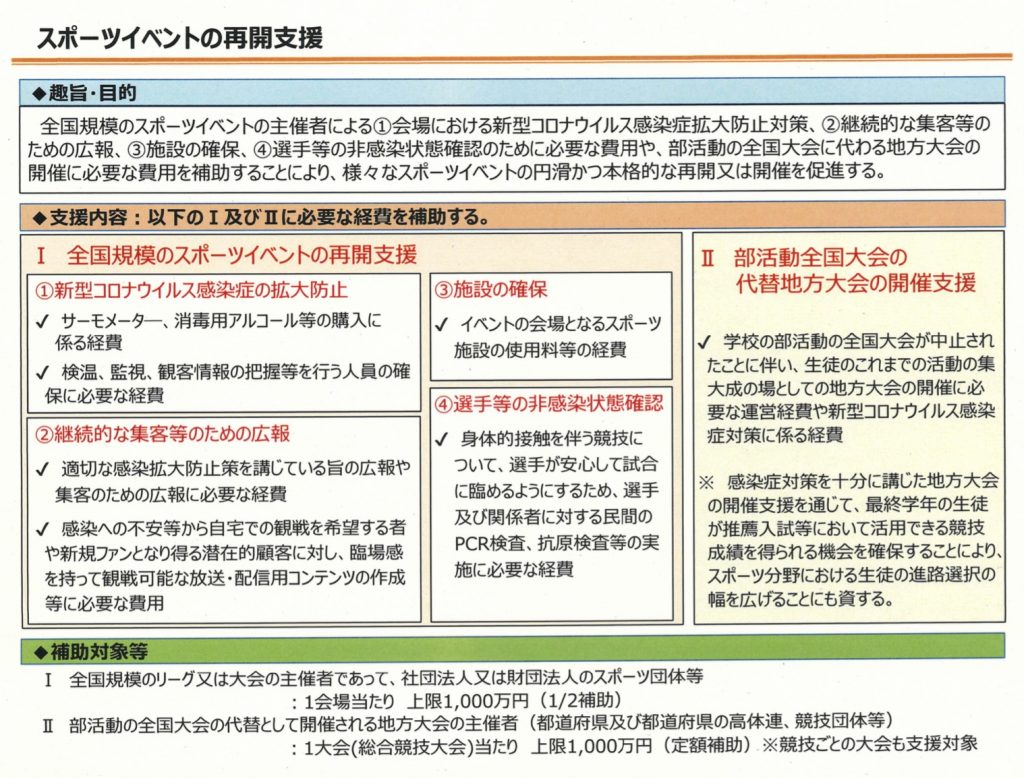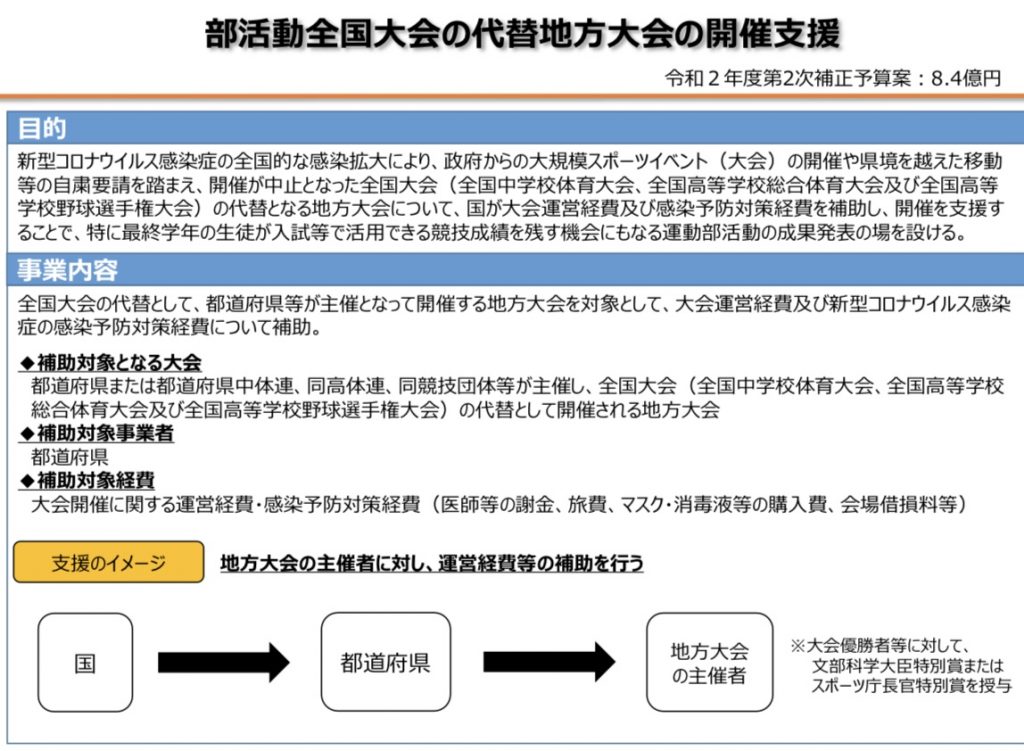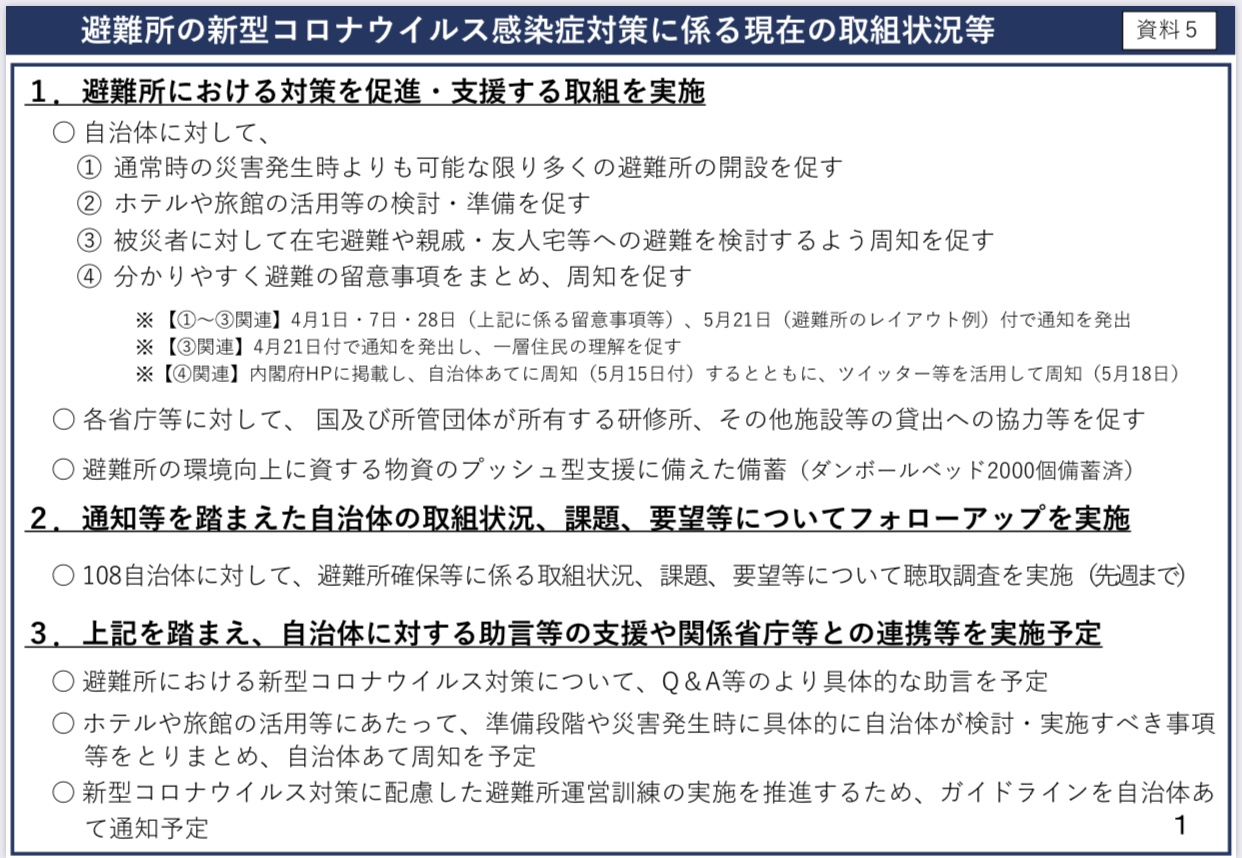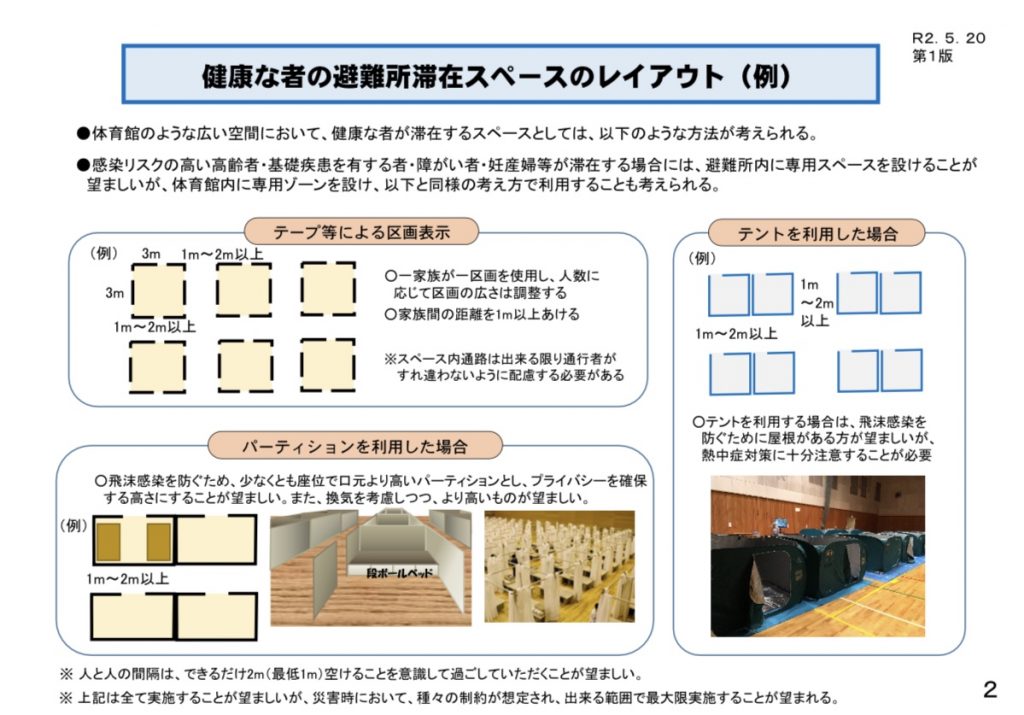本日、自民党秋季入学制度検討ワーキングチーム(柴山昌彦座長)による提言書を、安倍総理とともに受け取りました。
提言書によると、まず、COVID-19による学校休業に伴う《学びの保障》は喫緊の課題であり、《秋季入学制度》いわゆる9月入学は、国民的合意や実施に一定期間を要するため、2つの問題は切り離して検討することとしています。
《学びの保障》については、
・オンライン学習の推進とともに、①教育活動の重点化、②長期休業期間や土曜日の活用等が必要。
・設置者の判断で、令和2年度を2週間〜1か月など一定期間延長する特例措置を検討。第2波が生じた場合は、延長期間の延伸など柔軟に対応。大学等は、第一学年の始期のみ遅らせることを検討。
・入試方針を政府は早急に決定・公表。①大学入学共通テストを含め、日程は、2週間から1か月程度の後ろ倒しを検討。②大学・高等学校・中学校の入学者選抜は、最終学年の学習状況の影響等への対応を要請するとしています。
《秋季入学制度》については、
・秋季入学制度いわゆる9月入学は、国民的合意や法整備を含めた実施に一定の期間を要するため、今年度・来年度のような直近の導入は困難。秋季入学制度を含めた教育改革について、総理の下の会議体で、各省庁一体となって、広く国民各界各層の声を丁寧に聴きつつ検討すべきという内容です。
政府としては、6月1日から多くの学校が再開する中で、いかにして子供たちの学びを保障していくかを第一に考えます。また、特に入試や就職について、本人や保護者は不安に感じておられると思います。そうした不安の解消に向けて、本日の提言も踏まえ、関係省庁にしつかりと検討させる所存です。