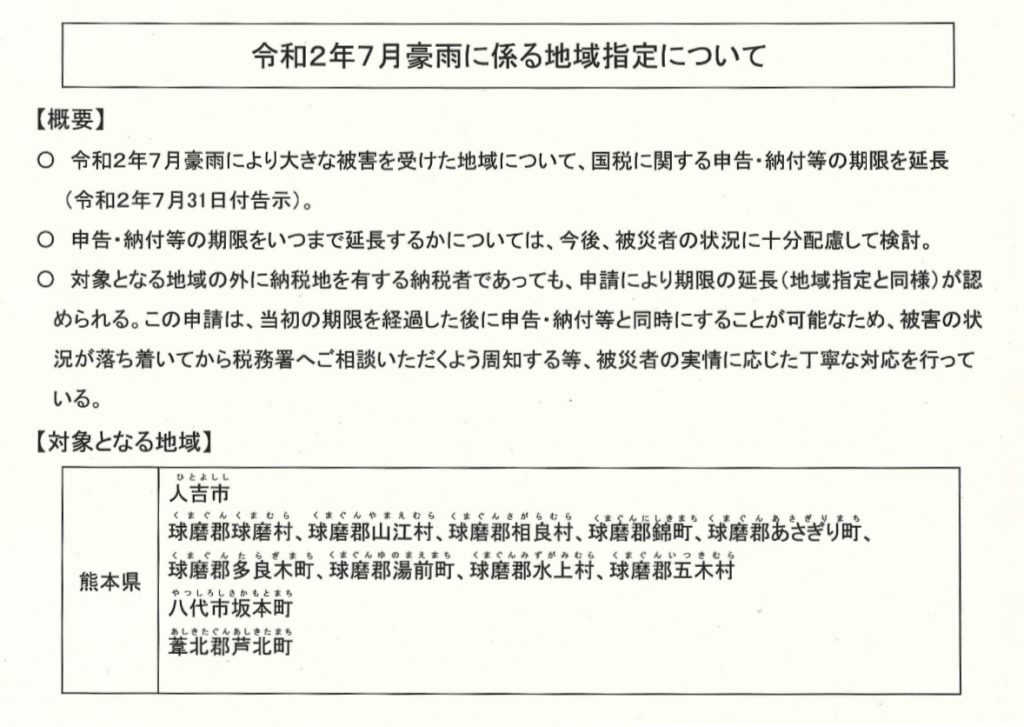先週のことになりますが、令和2年7月17日、厚生労働省の省議室に連合の神津会長を迎えて、第1回労働政策対話を行いました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/chihoubunken/index_00001.html
経団連では、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」や「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」の提言などを踏まえ、オフィス向けや製造事業場向けに《新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン》を作成しています。
一方、政府としても、感染拡大防止策の進化や医療提供体制の充実等に引き続き取り組んだ上で、雇用・事業・生活を守り抜くことを、目下の最重要課題と位置づけています。
このような中、個々の業界や事業所の実態に応じた新型コロナウイルス感染予防対策を行なう現場である『産業別労働組合』から、その実態を把握する機会をいただきました。そして、《新しい生活様式における働き方》をテーマとして意見交換しました。
今回の感染症拡大で、国民意識・行動に新たな動きが生まれています。その一つが《就業者の3分の1強がテレワークを経験》できたことです。テレワークをきっかけとして、柔軟で多様な働き方が大企業中心に急速に広まりました。
政府としても、新たな働き方やワーク・ライフ・バランスの取組の流れを最大限いかし、さらなる定着を図るため、また、中小企業への導入に向けて、専門家による無料相談対応や全国的な導入支援体制の構築を進めてまいります。
これから、withコロナでの労働分野において、どのような問題があるのかを、各々の産業の代表者と忌憚のない意見交換をしていく所存です。